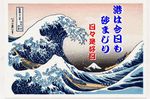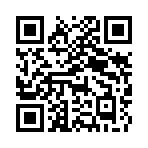2011年09月08日
レトロな羊羹の包み紙 展
ご案内頂いた町内のアートスペース、フェルケール博物館で
羊羹の包み紙とラベル展
を鑑賞して来ました。

収集家個人から寄贈された石の博物館所蔵のコレクションだそうです。
味見も出来ない、ようかんの包み紙だけなんてと思ったら、面白い。
いつも思いますが、収集家の執念と言うか、熱意には頭が下がる。
製造において、こんな食材が原材料になるかというもの〜素材語呂合わせの商品名。
和洋折衷のラベル、富士、櫻やその土地の特徴的風景は、土産にもらうと味と共に
観光気分も味わえるかも。
画像、写真を使っていないので、ほとんどがイラスト、絵画チック。
色使いや時代をあらわしているような、古風な書体もレトロ感を増す。
パッケージというより、包み紙という表現が合う。
一回りしたら羊羹食べたくなって来た。
全国の羊羹がありましたが、静岡にも結構変わった羊羹があったんですね。
松伯堂さんの山葵羊羹は食べてみたい。今でも作っているのかな。
ご存知清水の追分羊羹屋さんも、特別コーナーで展示されていました。
10日、11日には2階ホールにて、先着100名様に
グリーンフレンド(協)さんによる抹茶サービスがあるそうです。
★開催期間・平成23年9月3日(土)~10月2日(日)
↓入場料・開館日等はフェルケール博物館HPで
http://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/
羊羹の包み紙とラベル展
を鑑賞して来ました。

収集家個人から寄贈された石の博物館所蔵のコレクションだそうです。
味見も出来ない、ようかんの包み紙だけなんてと思ったら、面白い。
いつも思いますが、収集家の執念と言うか、熱意には頭が下がる。
製造において、こんな食材が原材料になるかというもの〜素材語呂合わせの商品名。
和洋折衷のラベル、富士、櫻やその土地の特徴的風景は、土産にもらうと味と共に
観光気分も味わえるかも。
画像、写真を使っていないので、ほとんどがイラスト、絵画チック。
色使いや時代をあらわしているような、古風な書体もレトロ感を増す。
パッケージというより、包み紙という表現が合う。
一回りしたら羊羹食べたくなって来た。
全国の羊羹がありましたが、静岡にも結構変わった羊羹があったんですね。
松伯堂さんの山葵羊羹は食べてみたい。今でも作っているのかな。
ご存知清水の追分羊羹屋さんも、特別コーナーで展示されていました。
10日、11日には2階ホールにて、先着100名様に
グリーンフレンド(協)さんによる抹茶サービスがあるそうです。
★開催期間・平成23年9月3日(土)~10月2日(日)
↓入場料・開館日等はフェルケール博物館HPで
http://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/
今では、全国いたるところに土地の名勝や名物を商品名にした羊羹や名物の食べ物を混ぜたりした名物羊羹があります。また、“丁稚羊羹”や“水羊羹”など製法による羊羹の種類も多いことから、包み紙には様々なデザインや地域性を見ることができます。
羊羹の語源は、今から2,000年以上前の中国の春秋戦国時代に考えられた料理の名前で、羊の肉や肝を入れたあつもの羹、つまり温かい羊肉のスープのことでした。それが日本に伝わり、
羊肉の替わりに小豆や小麦、葛の粉を煉って固めて、蒸して汁に入れるようになったといわれています。その後、戦国時代になると茶の湯の発達とともに茶菓子が盛んに作られるようになり、現在のような寒天に餡を加えて固めたり練り羊羹も作られるようになりました。明治時代になると、庶民でも盛んに旅行に出かけるようになりました。そこで、各地で観光土産として羊羹が作られるようになり、工場での製造業者も現れるようになりました。加えて包装にも工夫がなされ、多種の包み紙やラベルが作られるようになりました。
今回の展示は、TV番組の「開運 なんでも鑑定団」に裃姿で出演されていた添川清氏が収集されたものを財団法人石の博物館館長の酒井陽太氏が譲り受けたコレクションを中心に紹介します。
羊羹の語源は、今から2,000年以上前の中国の春秋戦国時代に考えられた料理の名前で、羊の肉や肝を入れたあつもの羹、つまり温かい羊肉のスープのことでした。それが日本に伝わり、
羊肉の替わりに小豆や小麦、葛の粉を煉って固めて、蒸して汁に入れるようになったといわれています。その後、戦国時代になると茶の湯の発達とともに茶菓子が盛んに作られるようになり、現在のような寒天に餡を加えて固めたり練り羊羹も作られるようになりました。明治時代になると、庶民でも盛んに旅行に出かけるようになりました。そこで、各地で観光土産として羊羹が作られるようになり、工場での製造業者も現れるようになりました。加えて包装にも工夫がなされ、多種の包み紙やラベルが作られるようになりました。
今回の展示は、TV番組の「開運 なんでも鑑定団」に裃姿で出演されていた添川清氏が収集されたものを財団法人石の博物館館長の酒井陽太氏が譲り受けたコレクションを中心に紹介します。
Posted by 八兵衛 at 19:10│Comments(6)
│イベント ガイド
この記事へのコメント
管理人さまへ
初めまして。私は若者たちがかつて力比べに使った「力石」の調査をしています。本町の西宮神社の力石についてお尋ねします。
西宮神社には3個の力石があります。そのうちの一個には「さし石 金杉藤吉 48メ」などの刻字がされています。発起人は魚河岸場連中。金杉藤吉は東京港区に生まれた有名な力持ちで、清水区を含めて東京などにこの人の刻字石が計8個あります。仲士として清水湊に入ったとき、清水の魚河岸の方たちが発起人となって力持ちの興行をしたものと思われます。藤吉は慶応3年~昭和13年にいた人ですから、その間に清水でこの石を頭上にさしあげ、その記念に西宮神社に奉納していったものと思われます。
前置きが長くなりましたが、神社等にこの人に関する奉納額、古文書、力持ち番付などありませんでしょうか。また、西宮神社に詳しい方や総代さんなどご紹介いただけないでしょうか。この場をお借りして唐突なお願いをしましたが、よろしくお願いいたします。
初めまして。私は若者たちがかつて力比べに使った「力石」の調査をしています。本町の西宮神社の力石についてお尋ねします。
西宮神社には3個の力石があります。そのうちの一個には「さし石 金杉藤吉 48メ」などの刻字がされています。発起人は魚河岸場連中。金杉藤吉は東京港区に生まれた有名な力持ちで、清水区を含めて東京などにこの人の刻字石が計8個あります。仲士として清水湊に入ったとき、清水の魚河岸の方たちが発起人となって力持ちの興行をしたものと思われます。藤吉は慶応3年~昭和13年にいた人ですから、その間に清水でこの石を頭上にさしあげ、その記念に西宮神社に奉納していったものと思われます。
前置きが長くなりましたが、神社等にこの人に関する奉納額、古文書、力持ち番付などありませんでしょうか。また、西宮神社に詳しい方や総代さんなどご紹介いただけないでしょうか。この場をお借りして唐突なお願いをしましたが、よろしくお願いいたします。
Posted by 雨宮 at 2011年09月11日 21:30
雨宮様こんにちは
よくお調べになっておられますね。確かに大きい力石があります。
そういう謂れがあったとは、知りませんでした。
お尋ねの件、後日お祭りを取りまとめておられる方に
お聞きしてみますが、もうすぐ、11月19日のおいべっさんの縁日には
神社の準備に総代、氏子さん、長老さんも準備にお集りになるので
その場でお聞きになっても、あれこれお話出来るかと思います。
よくお調べになっておられますね。確かに大きい力石があります。
そういう謂れがあったとは、知りませんでした。
お尋ねの件、後日お祭りを取りまとめておられる方に
お聞きしてみますが、もうすぐ、11月19日のおいべっさんの縁日には
神社の準備に総代、氏子さん、長老さんも準備にお集りになるので
その場でお聞きになっても、あれこれお話出来るかと思います。
Posted by 八兵衛 at 2011年09月12日 09:36
at 2011年09月12日 09:36
 at 2011年09月12日 09:36
at 2011年09月12日 09:36早速、ありがとうございます。
よろしくおねがいいたします。
よろしくおねがいいたします。
Posted by 雨宮 at 2011年09月13日 01:23
雨宮様
先日、お祭りをまとめておられる氏子の方、
今日清水湊の歴史に詳しい魚屋さんにもお聞き致しましたが、
番付け等の力石に関わる資料は心当たりが無いとの事でした。
残念な返答となってしまいましたが、
あの石を持ち上げる威勢のいい姿を
生で見てみたかった気も致します。
先日、お祭りをまとめておられる氏子の方、
今日清水湊の歴史に詳しい魚屋さんにもお聞き致しましたが、
番付け等の力石に関わる資料は心当たりが無いとの事でした。
残念な返答となってしまいましたが、
あの石を持ち上げる威勢のいい姿を
生で見てみたかった気も致します。
Posted by 八兵衛 at 2011年10月05日 17:30
管理人さま
ありがとうございました。
県内調査も無事終り、バタバタしていました。お返事が遅れてすみませんでした。
力石を担ぐ力持ち大会は今も行われています。姫路の天満宮の大会は無形文化財です。岡山の総社宮では岡山大学ウエイトリフティング部の協力で子供から老人まで参加。スペインなどでも盛んです。
西宮神社の力石、ぜひ大事にしてください。できれば説明板があったらなあと。過去の青年たちの熱気を伝えて欲しいと思っています。
ありがとうございました。
県内調査も無事終り、バタバタしていました。お返事が遅れてすみませんでした。
力石を担ぐ力持ち大会は今も行われています。姫路の天満宮の大会は無形文化財です。岡山の総社宮では岡山大学ウエイトリフティング部の協力で子供から老人まで参加。スペインなどでも盛んです。
西宮神社の力石、ぜひ大事にしてください。できれば説明板があったらなあと。過去の青年たちの熱気を伝えて欲しいと思っています。
Posted by 雨宮 at 2011年11月05日 05:10
★雨宮様。お力になれなくてすみません。
地域に住んでいると、普通に見ているモノが、
眠っている資源と言うか,お宝て゜ある事を
気づかせて頂きました。
力持ち大会等,素晴らしい伝統行事だと思います。
清水湊の西宮神社の力石も、歴史ある地域の
観光資源として活用出来るモノであるような気も致します。
あの境内でこんな面白い事が行われていた事実。
説明板はほしいですね。
地域に住んでいると、普通に見ているモノが、
眠っている資源と言うか,お宝て゜ある事を
気づかせて頂きました。
力持ち大会等,素晴らしい伝統行事だと思います。
清水湊の西宮神社の力石も、歴史ある地域の
観光資源として活用出来るモノであるような気も致します。
あの境内でこんな面白い事が行われていた事実。
説明板はほしいですね。
Posted by 八兵衛 at 2011年11月07日 20:45